
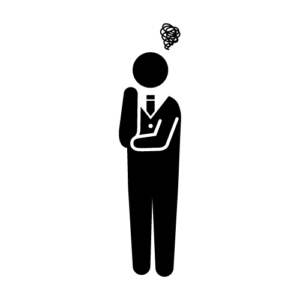
こんなお悩みを解決する記事になっています。
公費が絡んだ場合の高額療養費の限度額計算って難しいですよね。
高額療養に該当する患者さんが公費による診察も受けている時は、限度額計算がとっても複雑。
特に「公費分の点数を含めて限度額計算するのかどうか?」の判断が悩みどころ。
この記事では、公費を併用した場合の正しい高額療養費の限度額計算方法について解説します。
公費分の高額療養限度額は公費分の点数で計算

公費併用分で高額療養に該当した場合は、公費分の点数で高額療養費の限度額計算をします。
医保単独分の点数も含めて限度額計算しないよう気を付けて下さい。
社会保険診療報酬支払基金のレセプト請求計算事例を引用して解説します。
公費分で高額療養費
法別10結核医療との2者併用で異点数、かつ、10結核医療分で高額療養費が発生する事例です。

高額療養費の限度額計算は次の通りです。

先ほど解説した通り、公費併用分の高額療養費限度額は公費分の点数で計算します。
事例を見ると、公費分の点数85000点(850000円)で限度額計算していることが分かります。(緑で囲った部分)
医保分の高額療養費は21000円ルールで計算

通称、「21000円ルール」と呼ばれています。
公費分の点数×負担割合が21000円を超えたら、高額療養費は総点数で限度額計算します。(公費分の点数を合算して限度額計算)
こちらについても、社会保険診療報酬支払基金のレセプト請求計算事例を引用して解説します。
医保単独分で高額療養(公費分の点数を合算しないで限度額計算)
まず初めに、医保単独分で高額療養&総点数で限度額計算しないケースの解説です。

高額療養費の限度額計算は次の通りです。

赤く囲った部分が21000円を超えてないため、高額療養費は医保単独分の点数95000点(950000円)で限度額計算します。
限度額計算では、公費分の点数は合算しません。
医保単独分で高額療養(公費分の点数を合算して限度額計算)
次に、医保単独分で高額療養&総点数で限度額計算するケースの解説です。

高額療養費の限度額計算は次の通りです。

赤く囲った部分が21000円を超えているため、高額療養費は総点数の120000点(1200000円)で限度額計算します。
限度額計算では、公費分の点数を合算します。
医保単独分と公費併用分の両方で高額療養
稀ですが、医保単独分と公費併用分の両方で高額療養の限度額に達したケースを解説します。

高額療養費の限度額計算は次の通りです。

医保単独分は、赤く囲った部分が21000円を超えているので、高額療養費は総点数の180000点(1800000円)で計算します。
繰り返しになりますが、公費併用分は公費分の点数で限度額計算をします。(青枠部分)
公費分の自己負担が0円だと21000円ルール対象外

公費分の点数×負担割合が21000円を超えても、公費分の点数を合算して限度額計算してはいけないケースがあります。
古い情報ですが、社会保険診療報酬支払基金のレセプト請求計算事例を引用しながら解説します。

高額療養費の限度額計算は次の通りです。

公費分の点数×負担割合が21000円を超えています。(赤く囲った部分)
21000円ルールに該当しそうですが、医保単独分の限度額は、総点数ではなく医保単独分の点数で計算しています。(緑で囲った部分)
このように、公費併用分の自己負担が0円の場合、医保単独分の限度額は総点数ではなく医保単独分の点数で計算します。
まとめ

医保だけの診察、もしくは公費だけの診察であれば単純に高額療養の計算式に当てはめて計算すればOK。
厄介なのが、この記事で解説した公費併用で異点数の高額療養限度額計算です。
レセコンや電子カルテが自動で計算してくれればいいのですが、手作業で計算となると一筋縄ではいきません。
診療報酬支払基金の事例のように、枝分かれの計算式を駆使しながらようやく答えが導き出せる難解な数学です。
患者さんが払う医療費に直結する内容なので、計算ミスをしないよう心掛けたいです。
この記事を読んで、高額療養費に関する知識が深まれば幸いです。