
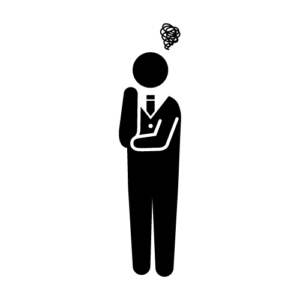
こんな疑問を解決する記事になっています。
北海道にお住まいの方で、いつもとまったく同じ診察内容にもかかわらず、冬になるとほんのちょっと医療費が高くなっていることに気づきませんか?
領収証だけ発行していると気付きにくいですが、明細書に「療養担当手当」という項目が冬限定で記載されます。
この記事では療養担当手当について詳しく解説します。
療養担当手当=暖房費

療養担当手当とはズバリ、暖房費のことです。
北海道地区にのみ認められている寒冷地手当とされています。
クリニック(病院)と歯医者さんでは金額が違います。
また、通院と入院でも金額に差があります。
| 通院 | 入院 | |
| クリニック(病院) | 7点(1月あたり) | 10点(1日あたり) |
| 歯医者さん | 12点(1月あたり) | 10点(1日あたり) |
1点10円なので70円~120円です。
6歳未満および70歳~74歳だとこのうちの2割、75歳以上だと1割、それ以外の方は3割なので、約10円~40円の上乗せとなります。
11月~4月の期間限定で徴収可能
暖房費なので患者さんから徴収できる期間が限られています。
徴収できるのは11月1日~4月30日まで。
電子カルテを導入しているのであれば、日付を見て自動的に計算してくれると思います。
自動計算の仕組みがない場合は、うっかり対象の期間以外で患者さんから徴収しないよう気を付けましょう。
患者さんから徴収するための条件がある

患者さんに医療機関に来てもらわないと徴収してはいけません。
言い換えると、医療機関内で対面による診察をした場合だけ徴収できます。
考えてみれば当然ですよね。
後ほど解説しますが、電話での診察なのに暖房費である療養担当手当を患者さんから徴収するのはおかしいです。
療養担当手当を患者さんから徴収してはいけないケースを具体的に解説します。
往診や訪問診療
医師や看護師が患者さんのお宅や老人ホームなどに訪問して診察する場合は徴収してはいけません。
診療点数早見表にもはっきりと書かれています。
往診治療のみで医療機関に患者が来診しない場合、患者の代理者(家族やその他のもの)が内服薬等を受取りにきた場合は、本手当は算定できない。(昭和34年1月9日 保医発138)
電話再診やオンライン診療
往診と考え方は同じです。
電話再診もオンライン診療も患者さんが直接医療機関に足を運んでいるわけではありません。
患者さんは医療機関での暖房の恩恵を受けてないので、療養担当手当を徴収するのはNGです。
次の記事で新型コロナの影響により初診から電話による診察が認められていると紹介しました。
-

-
【新型コロナ】電話再診を活用してリスクと医療費を減らす
新型コロナが怖くてかかりつけの医療機関に行くのに抵抗がある。 オンラインで診察してくれないの? こんなお悩みを解決する記事になってます。 国は新型コロナ感染拡大防止のため、医療制度を時限 ...
今まで以上に電話による診察のケースが増えているはずなので、うっかり徴収しないよう気を付けたいですね。
外泊
こちらも考え方は同じ。
医療機関に泊まるわけではないので、患者さんからの徴収はNGです。
因みに、診療点数早見表にはっきり明記されています。
入院患者が外泊の場合の当手当は、被保険者が暖房の利益を受けていないので請求は認められない。(昭和34年1月9日 保医発138)
即日入院の外来や退院日の外来
外来で診察してもらってそのまま入院。
退院した日にそのまま外来受診。
このようなケースで、外来で療養担当手当の徴収はNGです。
普通に考えて、同日の外来と入院それぞれで暖房費を徴収するのは非常識。
こちらについても診療点数早見表に書かれてます。
同一日内に入院より外来に、あるいは外来より入院に移る場合の外来は、ともに本手当の請求はできない。(昭和34年1月9日 保医発138)
まとめ

東北地方の医療機関からすると、療養担当手当は羨ましいだけのインセンティブでえこひいきな気がしますよね。
「東北地方だって、北海道に負けず劣らず寒いよ!」
と思わず突っ込みたくなる制度です。
電子カルテが普及している昨今、療養担当手当は自動的に計算してくれるので医療事務に携わる方が意識するケースは少ないはず。
でも、患者さんにとっては「塵も積もれば」の負担なので誤請求しないよう気を付けたいですね。
この記事を書きながら「温暖化で昔ほど寒くならなくなったら制度は廃止になるのかな?」なんてことを考えてしまいました。
療養担当手当について、この記事で少しでも知識が深まれば幸いです。
療養担当手当については診療点数早見表にも載っています。
2022年4月版の診療点数早見表はこちらからどうぞ。
